幼児教育・保育科「先生に聞いてみた」 葛谷先生
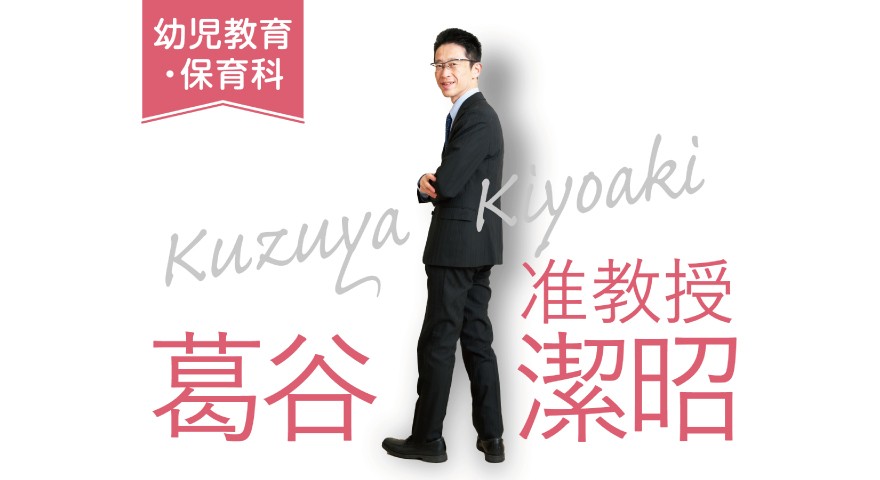
<所属・氏名>
短期大学部
幼児教育・保育科
准教授
葛谷潔昭(クズヤキヨアキ)先生
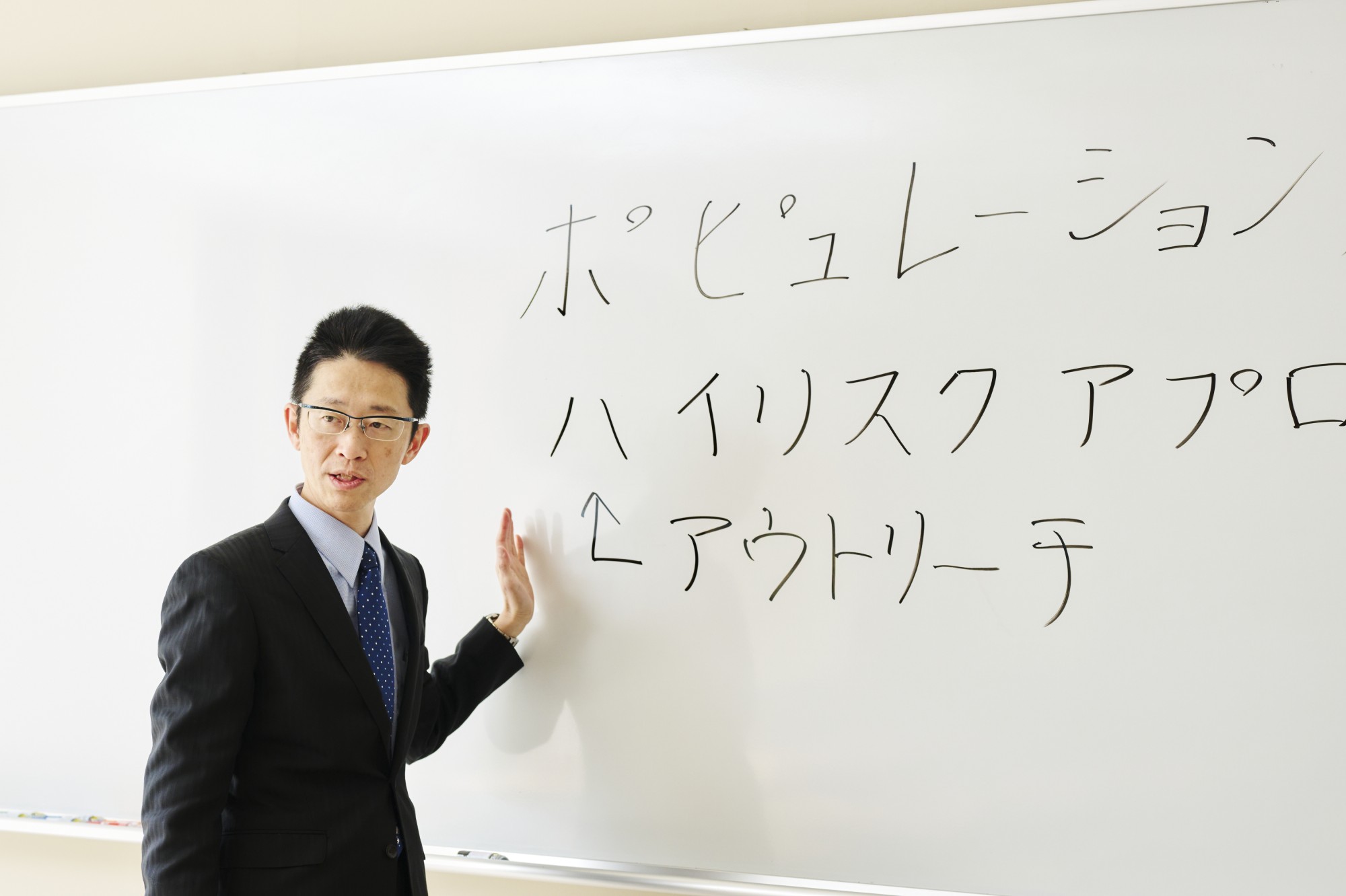
<基本情報>
これまでの経歴を教えてください。
福祉系の大学を卒業後、大学院に進学しました。大学院在学中は、在学している大学の事務室で研究企画担当として働いていました。大学院修了後は専門学校に就職し、社会福祉士や介護福祉士の資格取得のための学科を担当。その後、福祉系の大学や専門学校・短大の教員を経て、豊橋創造大学へ赴任しました。どの学校にも保育士や児童指導員に加え、介護福祉士や社会福祉士の資格が取得できる学科・コースがあったことが共通点で、今なお「福祉と保育」の専門職養成にはこだわりを持っています。
「福祉と保育」の分野と関わるきっかけはなんですか?
自身の人生経験や生い立ちにあると思います。母が独身時代に保育者をしており、家には絵本やピアノ、教材がたくさんありました。そして、家族に障害のある弟や寝たきりの祖母などがいて、「福祉と保育」の重要性を肌で感じる幼少期でした。学生時代はボーイスカウトや児童養護施設等のボランティアに参加し、特に大学生の時は、虐待を受けた子どもたちとの関わりを深めるために、障害児施設や児童養護施設などで実習をしました。これらの経験をもとに、「福祉と保育」を教え、その実習を担当する教員をめざすようになりました。

<教員・研究>
専門研究分野を教えてください。
専門分野は、ソーシャルワーク、子ども家庭福祉、障害児・者の発達と支援、インクルーシブ保育、ボランティア・NPOと多岐に渡っています。そして、大学院では福祉分野の経営学を学びました。自分で福祉のサービスや事業を立ち上げたいという想いとボランティア活動で学んだことを出発点に、地域の福祉施設の設立や運営に関わったり、その応援をしたりしています。本学では、幼児教育・保育科と保健医療学部で社会福祉分野全般を教えていますが、特に多くの授業時間数を担当しているのが、社会的養護です。虐待を受けた子どもの発達や心と行動の安定を図るための援助、そういった子どもが社会に巣立っていけるようなサポートについて教えています。
学生に指導をする上で大切にしていることは何ですか?
社会福祉をはじめとする社会保障施策・制度は複雑で、学生にとっては非常に難しいものです。そのため、自分たちの生活とつなぎ合わせ、身近な問題として学んでもらえるように工夫しています。また、これらの施策・制度は生活の問題を予防・解決するためのものです。関連しているニュースを取り上げつつ、その内容が学生にとって身近なことであると意識してもらうことが重要です。学生の世代に見合った社会生活上の課題を伝え、それに見合ったサービスやサポートにはどのようなものがあるのかについても学べるように工夫しています。そのため、私の授業ではドラマやアニメ、ドキュメンタリーを活用することが多いですね。
先生が考える豊橋創造大学の良いところを教えてください。
先生方が熱心で活発、学生の人柄がよく、みなさんフレンドリーに接してくださいます。地域社会の問題に敏感で、その解決のために誠実に向き合い、アイデアを出しつつ取り組み、成果を上げている。つまり、創造力豊かな人材を育てているという印象です。そのベースには、先生方が学生一人ひとりにフォローを行き届かせているという強みがあると思います。短期大学部創立40周年を機に「Care&Idea」の理念を掲げ、地域社会においてますます重要な存在として輝きを増していける大学だと思います。
幼児教育・保育科としてはどうでしょうか?
保育だけでなく福祉にも力を入れている、伝統と実績のある学科だと思います。保育や障害児福祉(障害児保育・療育)の分野では地域の信頼も厚く、保育技術や表現技法の指導には定評があります。学内にある地域子育て支援拠点「つどいのひろば」の運営協力や地域での保育の実践は、そのような実績の代表例です。地域のみなさんも困りごとを気軽に相談してくださるんですよ。

先生ご自身はどのような学生生活を過ごされましたか?
入学直前に阪神淡路大震災が発生し、入学先の大学のボランティアセンターのスタッフとしての活動に力を入れていました。私も、多くの学生ボランティアを被災地へと送りました。自分自身もボランティア活動に赴き、被災した子ども向けのイベントの企画運営をしたり、高齢者や障害者がお住まいの仮設住宅や福祉施設などで、生活のサポートをさせていただいたりしました。そこでできたつながりを活かしながら活動と研究を継続し、大学院の修士論文も阪神淡路大震災の被災地にある特別養護老人ホームを研究対象にしたものを作成しました。また、自主ゼミのメンバーで愛知県西三河地域の高齢者福祉施設を訪問し、情報を集め、困りごとを入力したら福祉サービスにたどり着くような「福祉ナビケーションシステム」や利用者さんの状況や提供したサービスを記録するシステムの開発を行い、学会などで発表したことも思い出に残っています。あと、弓道部でインカレに出たり、大学生協の活動にも力を入れたりしていました。
幼児教育・保育科を目指す高校生へのメッセージをお願いします。
人生は一度しかないチャンスです。いろいろなことに挑戦し、経験してくださいね。本学は、そのようなみなさんの想いや願いを応援する、素敵な、優しさに満ちあふれた大学です。気軽にオープンキャンパスに参加して、本学の「空気感」を感じ取ってください。みなさんとキャンパスでお会いできるのを楽しみにしております。

